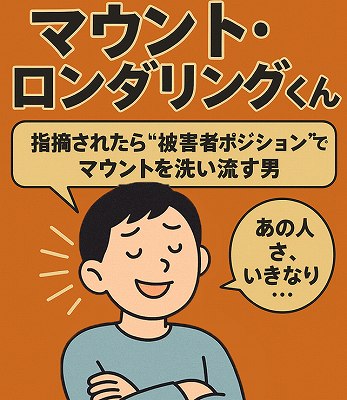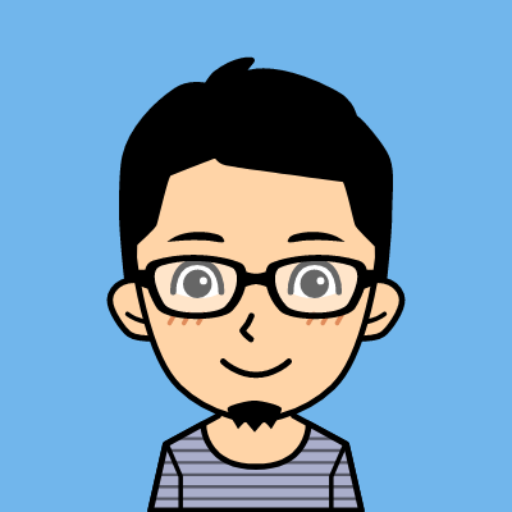指摘したら「被害者」になる同僚──マウントを"洗い流す"厄介な手口
どんな人か
普段はドヤ顔で自説を語る。 自信満々で、マウントも取ってくる。
でも、こっちが指摘した瞬間、空気が変わる。
急に伏し目がちになって、 「いや、そこまで言わなくても……」みたいな顔をする。
そして翌日には、同期にこう言ってる。
「昨日、○○さんにめっちゃ詰められて……正直キツかったっす」
こっちは普通に指摘しただけなのに、 いつの間にか「私がいじめた」ストーリーにすり替わってる。
これが、マウント・ロンダリング。
自分のマウントや攻撃性を、「被害者ポジション」で洗い流して、評価を守る手口。
あー、いるいる…… 先輩に注意されたら、翌日には「昨日すごい勢いで詰められて辛かった」って言いふらす人ね


そう、それ。
しかも本人は「勝った」と思ってるんだよね。
「周りは自分の味方」「あいつが悪者」って構図を作れたから。
根性が腐ってるのか、屈折してるのか……
多分どっちもじゃない?

実際にあった話──営業チームの朝礼での一幕
営業のKさんが、朝礼でこう言った。
「提案資料の"10%増"が"100%増"になってました。数字ミスは命取りなので、確認をお願いします」
名指しじゃない。 全員向けの、軽い注意喚起。
でも、その日の午後、別部門のLさんからこう聞こえてきた。
「Kさん、かなり強く言いましたよね? あんな言い方しなくても……」
え?
聞くと、ミスをした本人がこう言いふらしていたらしい。
「○○さんにめっちゃ怒られて、露骨に嫌な顔された。正直メンタルやられた……」
Kさんは普通に事実を伝えただけ。
なのに、見えないところで評価の"洗い流し"が完了してる。

これがほんとにタチ悪いのは、反論のしようがないところ
「そんなつもりで言ってない」って言っても、「いや、傷ついたのは事実なんで」で終わるもんね……


そう。 事実じゃなくて、感情の話にすり替えられるから、こっちが何を言っても悪者になる
このタイプがよくやること
- 最初はドヤ顔で自説を展開。ディスリに近いマウントも取る
- 指摘されたら急にしおらしくなる
- 「あの人、ほんと理不尽で……」と同期に共感を求める
- 自分が言った挑発的な言葉は、なかったことにする
- 直接反論せず、第三者経由で情報をねじ曲げて広める
- 会議中は元気だったのに、終わった瞬間「気まずかった」と漏らす
- SNSや社内チャットで「傷ついた自分」をアピール
要するに、裏で評判操作してるってことだよね。


そう。 しかも「傷ついた」っていう感情を武器にしてるから、周りも「まあまあ」ってなりやすい。
結果、指摘した側が悪者になる。
なぜそうなるのか
① 自己イメージを守りたい
自分の攻撃性やミスを認めると、自己イメージが崩れる。
だから、「被害者」になることで感情をリセットして、自分を正当化する。
② 評価が下がるのが怖い
周囲からの評価が下がることへの恐怖が強い。
だから、同情を集めて味方を増やすことで、自分の立場を守ろうとする。
③ 「物語」を作るのがうまい
事実をそのまま伝えるんじゃなくて、自分に都合のいいストーリーに編集して広める。
「詰められた」「怖かった」「メンタルやられた」…… 聞いた人は「そうなんだ、大変だったね」ってなる。

このタイプの厄介なところは、嘘はついてないこと。
え、どういうこと?


「傷ついた」っていうのは、本人の主観としては本当かもしれない。
でも、それをどう伝えるかで、事実がねじ曲がる。
「注意された」と「詰められた」は、同じ出来事でも印象が全然違うでしょ。
あー……言葉の選び方で、相手を悪者にできるってことか。

どう対処すればいいか
① 1対1で指摘しない
これが鉄則。
1対1で言うと、「何を言ったか」じゃなくて「どう感じたか」の話にすり替えられる。
だから、必ず第三者がいる場で伝える。
- チームミーティング
- Slackのオープンチャンネル
- 全員に共有される議事録
「複数の目がある」「記録が残る」環境なら、"演出"の余地がなくなる。
② 感情を入れず、事実だけを伝える
「ちゃんとやってよ」みたいな言い方はNG。
数字と事実だけを淡々と伝える。
「資料の数字、10%が100%になってました。修正お願いします」
主観を入れないことで、「嫌な言い方された」という解釈の余地を消す。
③ 最初に「目的」を宣言する
指摘の前に、ひと言添える。
「これは改善のためのフィードバックです」 「今後に向けた確認なので、共有しますね」
これだけで、「個人攻撃」という印象操作を防ぐバリアになる。
④ 評価を「成果ベース」に寄せる
評価が「なんとなくの印象」で決まる組織だと、ロンダリングが成立しやすい。
だから、測れる指標で評価する文化を作る。
- KPI、OKRなどの数値目標
- 成果物の品質チェック
- 定量的なフィードバック
「いい人っぽい」「かわいそう」という感情票が入りにくい土俵を作る。
なんか、対処法っていうより「防衛戦」だね……


そう、まさに防衛戦。
このタイプは「感情の土俵」に引きずり込んでくるから、最初から事実の土俵に固定するしかない。
やってはいけないこと
- 1対1で注意する → 「言った・言わない」の泥仕合になる
- 感情的に反論する → 「ほら、やっぱり怖い人」で終わる
- 「そんなつもりじゃなかった」と弁明する → 相手の「傷ついた」を認めることになる

大事なのは、相手を変えようとしないこと
え、変えなくていいの?


変わらないから。このタイプは。
だから、「その手口が通用しない環境」を先に作る。
人を変えるんじゃなくて、構造で封じる。
まとめ
マウント・ロンダリングの厄介さは、反論しにくいところ。
「傷ついた」という感情を盾にされると、こっちが何を言っても悪者になる。
事実がねじ曲げられて、評価が洗い流されていく。
だからこそ、
- 1対1を避けて、オープンな場で伝える
- 感情を入れず、事実だけを共有する
- 評価を数字と成果に寄せる
相手の「物語」に支配される前に、客観的な土俵に固定する。
人格を変えようとしなくていい。 「その手口が通用しない構造」を、先に敷いておく。
それがいちばん現実的で、いちばん賢い対処法。