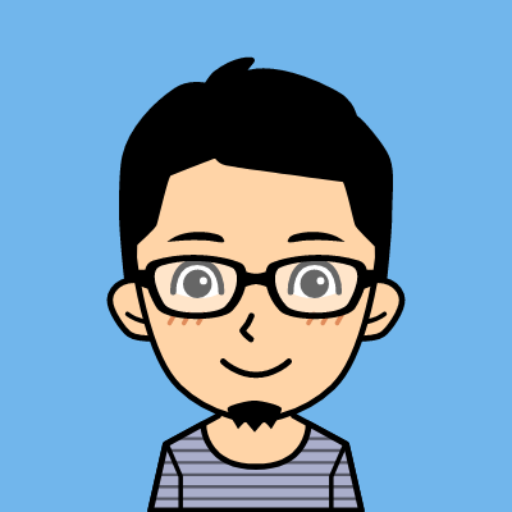親の七光りで「無敵状態」の後輩──注意しても届かない、逃げ場のない現場の話
どんな人か
vol.1の「なめくさり後輩くん」には、進化系がいる。
それが、親や上層部の権力を背景に持ってるタイプ。
実力不足なのは周りも気づいてる。
でも、「あの部長の息子だから」「役員のコネ入社だから」という空気で、誰も何も言えない。
本人もうすうすわかってる。
でも、根拠のない自信+親の権威+若さという三重バリアで、完全に無敵状態。
指摘しても響かない。
それどころか、下手に関わるとこっちが損をする。

これ、vol.1「なめくさり後輩くん」より厄介なんだよね。
「実力がないのに自信がある」だけなら、まだ気づかせようがある。
でもこっちは、構造的に手が出せない。
注意したら「あの人、○○部長の息子に目つけてる」とか言われそうだよね……


そう、それ。
まともに接すれば接するほど、自爆リスクが上がる。
この時、現場にいるこちらはこうなる
- 「言いづらい…」という空気に支配される
- 指摘すれば、「目をつけられた」と感じ取った親が水面下で動きかねない
- まともに接すれば接するほど自爆リスクが上がる
実際にあった話──ある営業部での一幕
Bくんは、社内の有力部長の息子。 「若手抜擢」という名目で配属されたけど、現場の誰もが「まだ早いでしょ」と思ってた。
ある商談で、Bくんが独断でクライアントに値引きを約束してしまった。 しかも、社内承認を通さずに。
先輩が「それ、ちゃんと上に確認した?」と聞くと、
「大丈夫っすよ、僕の判断で。向こうも喜んでましたし」
結局、あとから上司がフォローに走り回ることになった。 でも、Bくんにはお咎めなし。
それどころか、部長から「Bも頑張ってるんだから、みんなでサポートしてやってくれ」と言われる始末。
現場に静かな「割を食わされた感」が積もっていく。
これ読んでるだけで胃が痛くなる……


しかもこういうの、本人は「自分は期待されてる」って思ってたりするんだよね。
周りがフォローしてくれてることにすら気づいてない。
なぜ「無敵状態」になるのか
① 誰も注意できない構造
「あの人の息子に何か言って、あとで親が自分に目を付けたらどうしよう」 この面倒さが、現場の口を塞ぐ。
② 忖度する人たちが周りを固める
同期や「うまくやりたい派」の人たちが、表面上は仲良くする。 だから、本人は孤立しないし、問題にも気づかない。
③ 組織が「見て見ぬふり」を選ぶ
上司も「面倒ごとに関わりたくない」から、スルーする。 結果、黙認の空気ができあがる。

つまり、本人の問題というより、それを許してる環境の問題なんだよね、本当は。
でも、環境を変えるなんて現実的に無理じゃない?


まさにそう。
だから「正面突破」は諦めた方がいい。
別のやり方がある。
どう対処すればいいか
① 「人」ではなく「成果」に焦点を当てる
「Bくんがダメだ」と言っても、守られて終わり。
だから、人ではなく、アウトプットの話にする。
「今回のプロジェクト、この部分の精度が低かったですよね。原因は何だと思いますか?」
事実ベースで「仕組み」や「成果物」の問題として可視化する。 そうすれば、感情の衝突を避けられる。
② 「外部の目」を使う
社内で言っても握りつぶされる。
だから、外の評価を入れる。
- クライアントからのフィードバック
- 外注先のレビュー
- 匿名アンケート
第三者の声なら、「あいつが言ってる」で片付けられない。
③ 本人ではなく「周囲」を固める
直接ぶつかっても消耗するだけ。
だから、Bくんの周りのキーパーソンにアプローチする。
「Bくんのサポート、どうしたらいいですかね?」
という相談の形で、間接的に監視と教育の網を張る。
④ 記録を残す
このタイプと関わると、あとで「言った・言わない」になりやすい。
だから、やりとりは必ず記録しておく。
- メールやチャットで残す
- 判断の経緯をメモする
- 成果物は日付付きで保存
自分を守るための「客観ログ」。 何かあったときの防具になる。
なんか、対処法っていうより「生存戦略」だね……


そう、まさにそれ。 このタイプ相手に「正しさ」で戦っても勝てない。
だから、傷つかない位置で、じわじわ外堀を埋めるしかないだよね。
やってはいけないこと
・感情的にぶつかる → 「あの人、Bくんに嫉妬してる」で終わる
・一人で声を上げる → 孤立して、自分だけが損をする
・正論で追い詰める → 親が出てきて、状況が悪化する

組織って、正しい人が勝つとは限らないんだよね。 悔しいけど、それが現実。
じゃあ、泣き寝入りするしかないの?


そうじゃない。 「声を荒げずに、暴走できない土壌を作る」っていう戦い方がある。 時間はかかるけど、いちばん現実的で、いちばん賢い。
まとめ
「七光りの無敵くん」は、本人の問題というより、構造の問題。
注意しても届かない。 成長も促せない。 やがて周囲があきらめて、「黙認の空気」ができあがる。
これは、組織の透明性の低さ、評価の曖昧さ、育成の放任が生んだ制度的な死角。
だからこそ、個人を責めても意味がない。
「人」ではなく「仕組み」に手を入れる。
正面からぶつからず、外堀を埋める。
劇的な改革じゃなくていい。 見過ごされてた不都合に、一つずつフタをしていく。
それが、自分を壊さずに、現場を守るためのいちばん現実的な戦い方。

vol.1とvol.2は、「後輩」の話だったよね。
次のvol.3からは、もっと厄介な相手が出てくるかも。